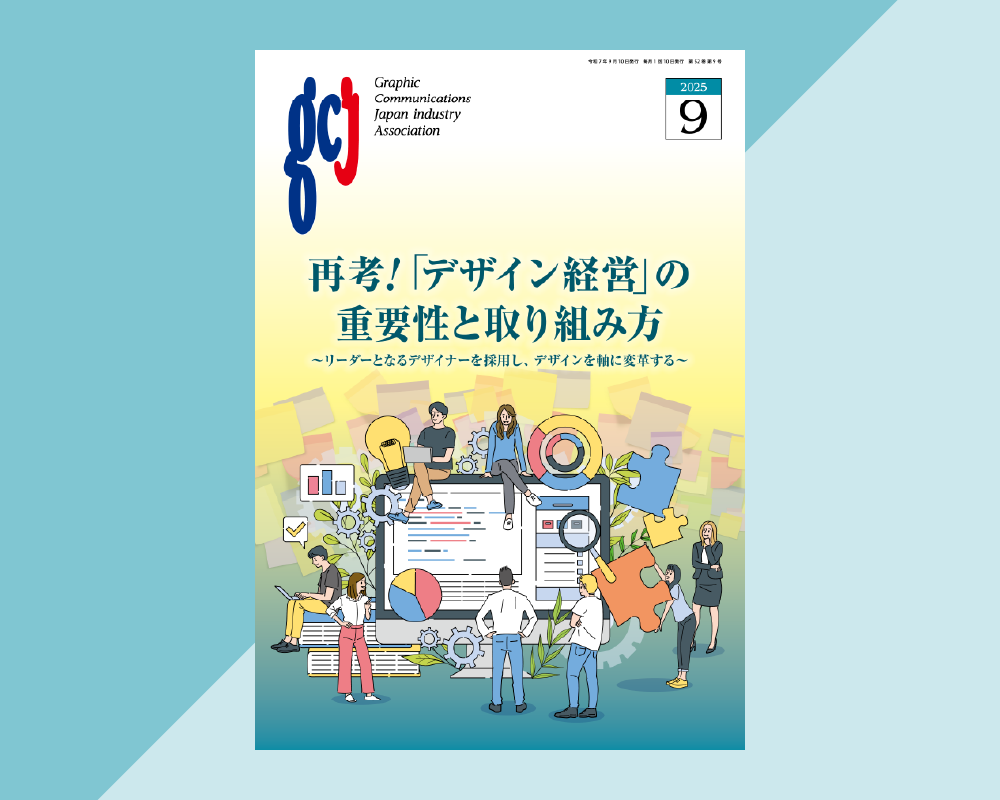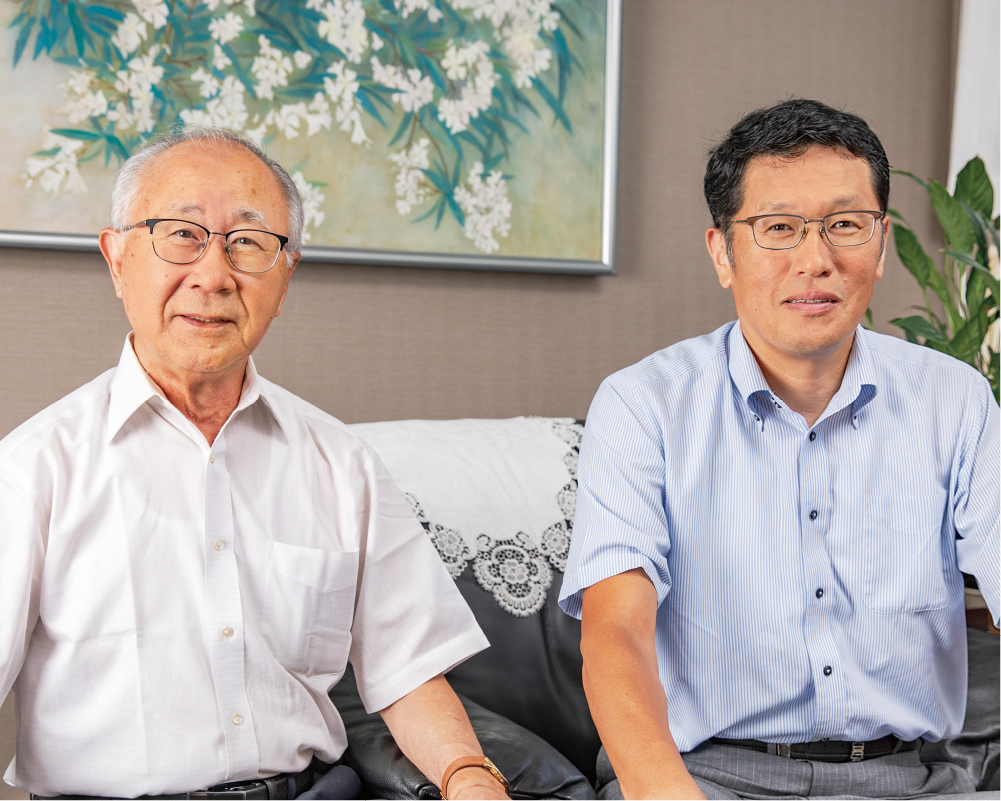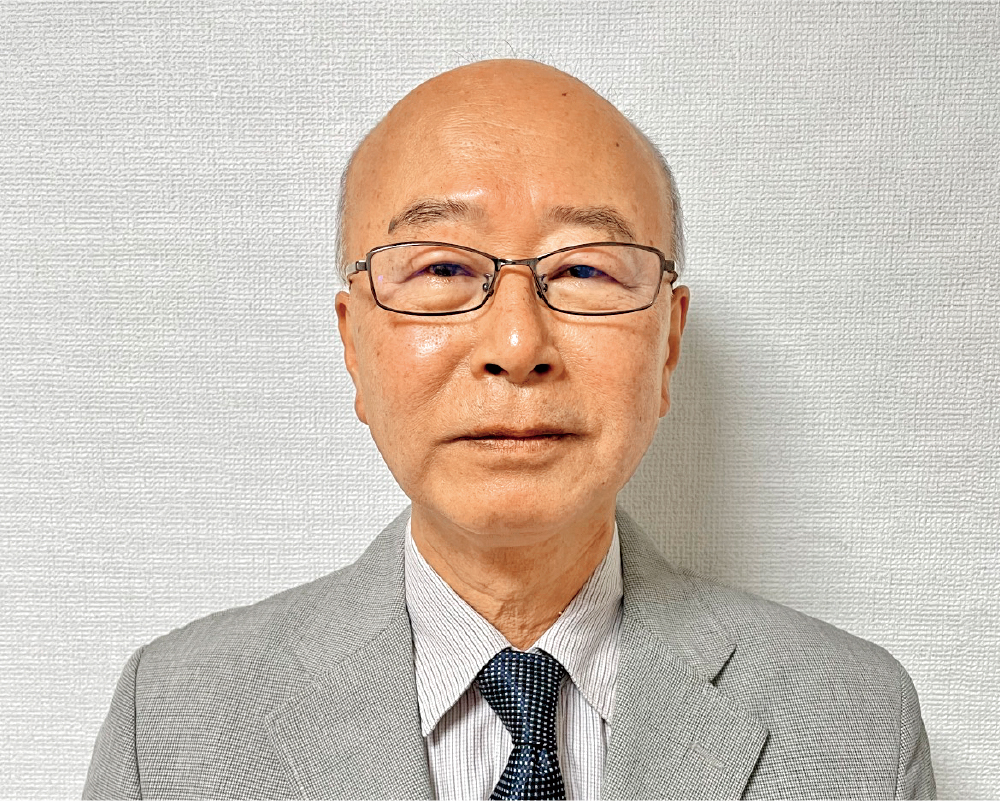バリアブルフォントの特徴と活用の可能性


今回は、株式会社モリサワが7月25日に「UI設計のためのフォントフォーマットを考える ~今さら聞けない基本から最新バリアブルフォントまで~」をテーマに開催したウェビナーを紹介する。講師は、同社東京サポートセンターの長谷川昌紀氏。モリサワは今年2月にバリアブルフォントをリリースしたが、ウェビナーではそのバリアブルフォントの特徴と活用法について解説した。同フォントの設定方法やメリットを説きつつ、何ができるのか、デザインはどう変わるのかなどについて話した。DTP制作会社や印刷会社にとっては、媒体を制作する上で新しい活用の可能性を知る機会になったと言えるだろう。

レクチャーズ・ルーム 69
株式会社モリサワ 東京サポートセンター
長谷川 昌紀 氏(講師)
バリアブルフォントとは、1つのフォントをさまざまな形に対応できるよう可変機能が搭載されたフォントで、1つのフォントファイルに複数の原型デザインを内包し、それらを動的に補間処理することで、多様なデザインを柔軟に生成できるようになっている。
「それぞれのパーツがあって、フォントの数値設定を動かすことによってフォントの太さを変えることができますし、場合によっては座標も変えられます。これらの動作を組み合わせることで、バリアブルフォントを自在に実現することができます」という。
そもそもバリアブルフォントの規格そのものは、2016年にOpenType1.8として公表されたものであり、これは1990年代初頭に存在したマルチプルマスターフォントやTrueType GXといった技術まで遡る。ただ、当時は対応アプリケーションやフォントの種類が限られていたため、結果的には普及には至らなかったという。
従来のファミリーフォント(スタティックフォント)は、ウエイトや字幅ごとに個別のフォントファイルが用意されていたが、バリアブルフォントはそれらの複数のフォントファイルを、1つのファイルとして効率的に集約できるのが特徴である。そのため、Webサイトなどのデジタルコンテンツに組み込むことで、フォントデータの容量を削減できる効果があるという。
今年2月、モリサワは和文バリアブルフォント「DriveFlux」をリリースした。このフォントはグラフィックユースを想定した新規デザインで、4つのデザイン軸を搭載している。長谷川氏は、このバリアブルフォントの動かし方について、「軸情報には『太さ』『幅』『イタリック』『傾き』『オプティカル』の5種類があり、その中の最低1つ以上の軸情報を可変情報としてフォントに入れることで、バリアブルフォントを形成することができます。また、ユーザーが自由な形でバリアブルフォントを作成できる“カスタム軸”と呼ばれる軸も別途用意しています」と話す。
そのため、「軸情報をどれだけ用いるか、登録するか、あるいは処理させるかが、バリアブルフォントを使う上での肝になる」と、長谷川氏は指摘する。フォントの扱い方によってデザインに影響が出ると言えるだろう。さらに、カラーを軸として設定することで、カラーのバリアブルフォントを作成することも可能だという。
従来のスタティックフォントは、「ライト」「レギュラー」「ミディアム」「ボールド」「エクストラボールド」「ヘビー」「エクストラヘビー」「ウルトラ」の8ウエイトを用意しているが、1つのウエイトに対して1つのフォントファイルが必要となるのが基本である。そのため、太さに合わせてフォント数を用意しなければならない。一方、バリアブルフォントは、1つのフォントファイルだけで完結できるのが最大の特長となっている。
続いて、バリアブルフォントの用途について、カーナビゲーションの画面事例を用いて説明した。「通常のカーナビでは、夜間においても文字の表示は変わらないと思うが、視認性を考慮した場合、文字の太さや色を変えたり、背景を変えたりするほうが良いことはご理解いただけると思います。バリアブルフォントを使えば、瞬時にフォントを調整したり、パラメーターを差し替えて見やすくしたりすることができるようになると思います。そして、ユーザーごとに視認性の高い表示方法を設定することが可能になるでしょう」と、バリアブルフォントの今後の可能性を示した。バリアブルフォントが真価を発揮する時代が来たと言えるだろう。
|