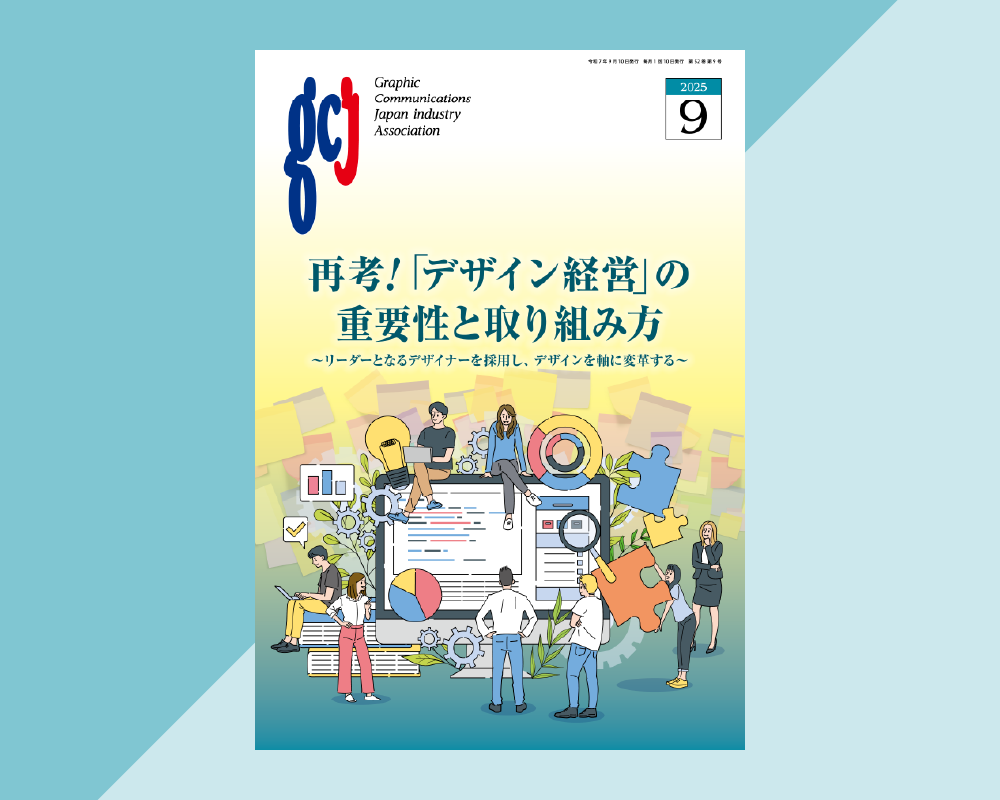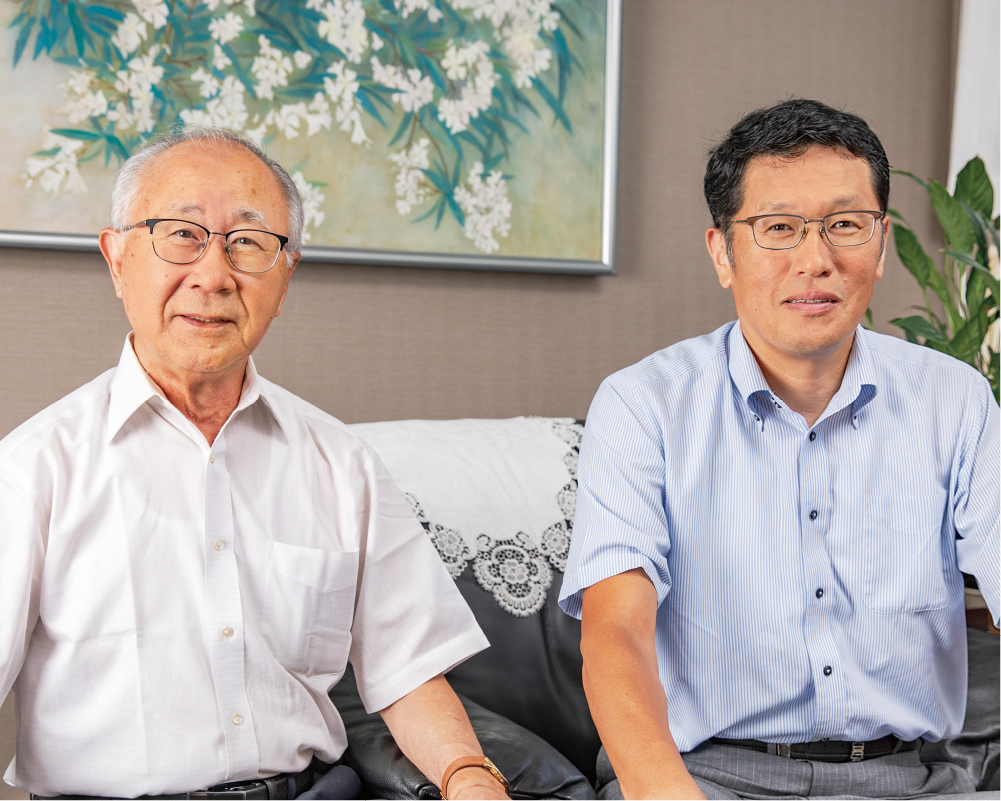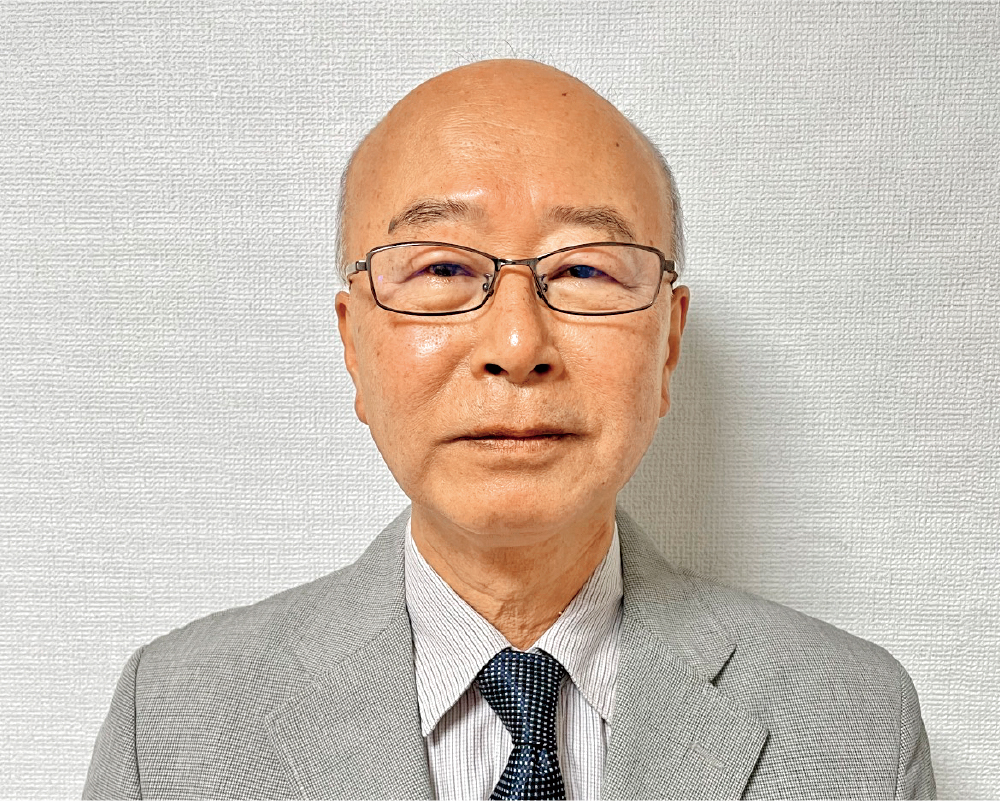CTIシステムを活用した営業の仕組みづくりを

今回は、4月22日に株式会社イノーバが主催しオンラインで開催した「売れる営業の“強み”を可視化! ~仕組みと指標で営業×マーケを強くする」のセミナーから、株式会社RevComm Field Sales groupグループ長の佐藤誠氏の講演内容を紹介する。佐藤氏は、架電から始まる営業において、音声解析技術を活用した高機能のCTIシステムの活用を促している。営業品質を高めて受注に繋げるために、営業活動の可視化やトップセールスのトーク力を分析し、個々の担当者の改善を図ることを説く。また、データの可視化によってセルフコーチング環境の重要性が高まると述べている。印刷業も、営業においては架電でアポイントをとることが多いため、CTIシステムを使った営業の仕組みづくりは有効である。

レクチャーズ・ルーム 67
株式会社 RevComm Field Sales group グループ長
佐藤 誠 氏(講師)
冒頭、佐藤氏は「営業で受注数を増やす方法として最も手っ取り早いのは、架電数を増やすことです。要は量を増やせば短期間で成果を出すことが可能であり、またマネジメントもしやすいのが利点です」と話す。
しかし、架電などアプローチの量をただ増やすだけでは、落とし穴が存在することも指摘する。「架電によるアプローチの量を増やせないなら、あとは質を高めていくしかありません。ただし、質を求めれば量を極端に減らして良いのかと言えばそうでもありません。量はある程度担保しつつ質もしっかりと高めていく必要があります」と述べ、「質」と「量」車輪を動かしていくことが重要だと指摘する。
「質」の向上の仕方について、佐藤氏はインサイドセールスの観点から述べている。「実際のところは、質を向上させるのはなかなか難しいものです。インサイドセールスでは、1人の担当者が非常に多くの見込み客に架電します。1日で1人が50コールしていたとすると、100人であれば全体で5,000コールになります。これらすべてのコールをトラッキングするのは、数が多すぎて現実的に不可能と言えるでしょう。1件ずつトラッキングをして何か課題を見つけたいと考えても、そもそも数が多いため難しいのです」と話す。
しかし、トークのどこに問題があるのか、あるいは、受注に成功した要因はトークのどこにあるのかといったことを、言語化するのは相当に難しい。「PDCAにおいては、『プラン(計画)』と『ドゥ(実行)』までは量をたくさんこなすことが主体になりますが、一方で『チェック(評価)』と『アクション(改善)』で課題を見つけるのは難しくなります。逆を言えば、『チェック』と『アクション』をしっかりと行うことができれば、インサイドセールスを向上させるマネジメントが確立できます」と説く。
佐藤氏は、「顧客とのコミュニケーションに焦点を当てて、架電数や通電数(相手が電話に出て話した数)、アポイント数に目を向けて、それぞれどこに問題があるのかを可視化することが重要です」と指摘する。
そこで、ステップごとに必要なポイントについて言及した。「まず課題の特定というところでは、架電数、通電率、通電後のアポ獲得率、さらにはアポ後の受注率、受注金額のどこに問題があり未達になっているのかを特定することが重要です。その上で、架電数が少ない原因はどこにあるのか、架電ができない要因があるのか、通電率を上げるためには何をしたら良いのか、どの時間帯に架電すれば良いのか、通電できてもアポイントがとれない場合はどこに問題があるのか、それぞれの原因を分析し明確にし、最終的にその原因をフィードバックしていくことが大切です」と、架電営業におけるPDCAの重要性を説いた。
また、架電業務でPDCAサイクルを機能させるにはツールが必要だという佐藤氏。その有効な手段の1つが、CTIシステム(コンピュータと電話・FAXを連携させるシステム)だという。「さらに、顧客情報の管理を効率的に行うCRMと連携できる高機能なCTIシステムを使えば、顧客との通話の文字起こしや録音などができ、話した内容を定量的に解析することで、架電が上手くいかない原因を見つけることができます。そこから架電をした担当者の問題点を改善していけば良いわけです。実際にCTIシステムで分析された内容を見れば、担当者自身でも問題点が把握でき、納得感を得ることができるはずです。また、ツールのデータを活用すれば、トーク力のあるベテラン社員との違いが分かり自己研鑽ができるため、セルフコーチング環境を整備することもできます」と、CTIシステムを構築して売れる営業の仕組みを可視化することの有効性を述べた。
|