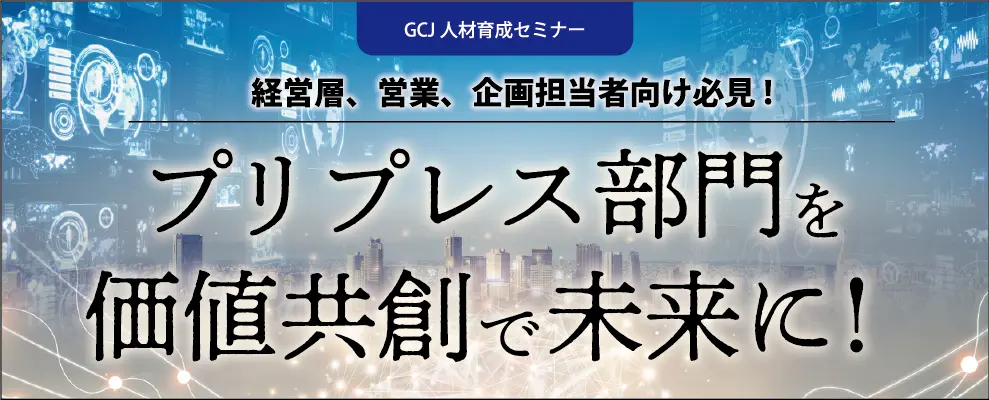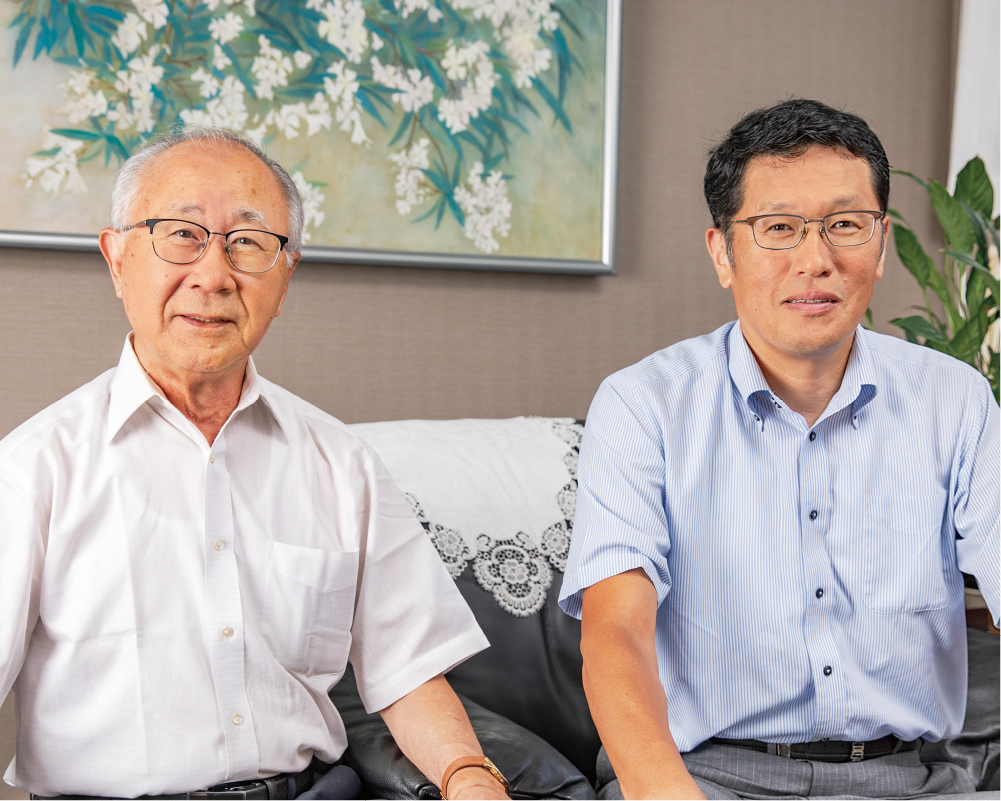電子出版市場編
データは語る
電子書籍や電子雑誌はさまざまな原因が重なって低迷している
(公社)全国出版協会・出版科学研究所によると、2024年の電子出版市場は、前年比5.8%増の5,660億円となりました。内訳は電子コミックが5, 122 億円(同6. 0% 増)、電子書籍が452億円(同2. 7%増)、電子雑誌が86億円(同6.2%増)とのことです。
電子出版市場は、この10年間で5倍に拡大したものの、その要因は電子コミック市場の拡大によるところが大きく、全体の9割を占めていることから、電子コミックが電子出版市場をけん引していることが分かります。
一方で伸び悩んでいるのが電子書籍です。電子雑誌に至っては、ここ数年低迷が続いており、むしろ減少傾向にあります。電子書籍の市場が伸びない原因としては、そもそも読者が紙の書籍で本を読みたいという電子書籍や電子雑誌はさまざまな原因が重なって低迷している気持ちが強いことが挙げられます。その背景には、視認性の良さや紙の手触り、匂いといった感覚的な魅力を重視している読者が多いことが考えられます。
その他にも、紙の書籍で読書したほうが記憶が高まりやすい、紙の書籍を収集することを楽しみにしているといった理由が考えられます。一方で、出版会社自体が電子書籍にさほど注力していない、といった業界の問題もあり、それが原因で電子書籍市場が伸び悩んでいるという見方もあります。
また、電子雑誌が低迷している原因としては、これは電子書籍にも言えることですが、活字離れが進行している点が挙げられます。インターネット上にはニュース記事やブログ、SNSなどの無料コンテンツが溢れているため、一般的な情報については、わざわざお金を払ってまで電子雑誌を購入して読むというニーズが低いと言えます。
また、出版社目線で言えば、電子化によって広告収入が減少し、採算の取れるビジネスモデルの構築が難しいという面があります。また、出版社の電子化への対応の遅れ、権利処理の複雑さ、プロモーション不足なども考えられます。
さらに、紙と比べて視認性に劣る点や、読書以外にも多様な趣味を持つ人が増えていることなども挙げられます。
しかし、電子出版を発行する側や執筆者の立場からすれば、AIを活用することで、短時間で文章を構成したり執筆を支援したりすることが可能になり、制作時間の短縮化、低コスト化が実現できるため、電子出版市場の将来は明るいと言えるでしょう。

印刷会社もセルフ出版で出版業界に進出可能に
出版業界はデジタル化を通じて、将来のビジネスモデルを見直して新たな収益源を模索している段階にあると言えます。
さらに、執筆者自らが出版社を介さずに直接読者に届ける「セルフ出版」が1つのジャンルとして確立されつつあります。これはコスト削減やクリエイティブな制作、出版工程の時短に繋がるというメリットがあるため、今後、セルフ出版はますます拡大していくでしょう。それに伴い、クオリティをいかに確保していくのかという問題も浮上してきます。編集や校正、デザイン性、ターゲットの明確化、プロモーションの方法など、個人でできることには限界があります。
ビジネスとして収益を考えるのであれば、やはり編集者や出版社などのプロフェッショナルを介して出版することが、重要になってくるのでしょう。
いずれにしても、将来はデジタル化やインターネットの高速化が一層進んでいくでしょうから、電子出版の成長は期待できます。
DTP 部門を持っている印刷会社は、DTPデータの編集やEPUB形式への対応などのノウハウを持っているため、電子出版ビジネスに参入しやすい面があります。ワンソース・マルチユースを実現するために、紙の定期刊行物や冊子だけでなく、電子書籍にも視野を広げ、動画や音声を含むマルチメディアとして電子出版分野に進出することも考えたいものです。
また、国内外の電子出版市場の動向や、Amazon Kindle Direct Publishing、Apple Books、Google Play Books、Kobo Writing Lifeなど、電子出版プラットフォームの仕様や知識を得て、適切な販売戦略を考えられるようにしておくことも重要です。
これらを実現することで、印刷会社も電子出版で新しいビジネスチャンスを掴むことが可能だということが分かります。自ら書籍のテーマに関するアイデアや企画を考え、適切な執筆者を探して電子書籍の出版ビジネスを始めるのも、一考する価値があると言えるでしょう。
|