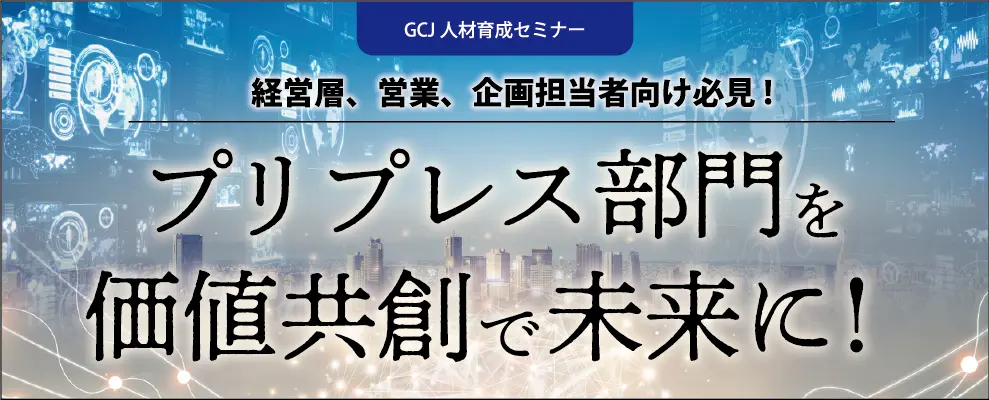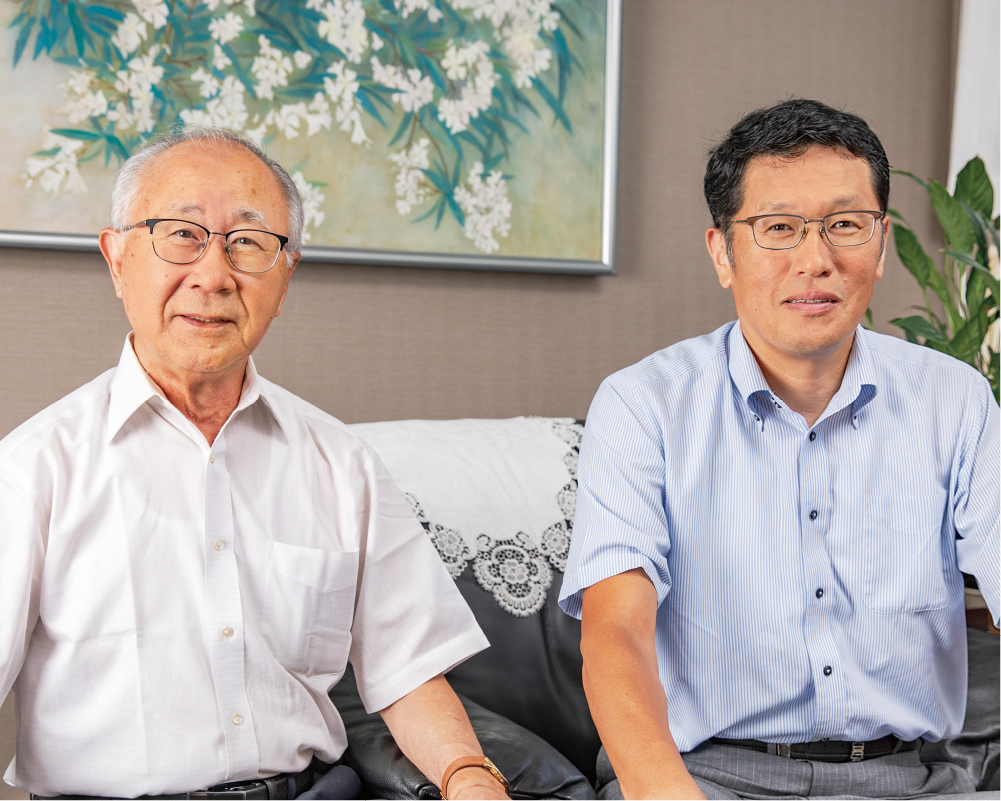最適な提案を行い営業活動を支援する
画像処理・DTP・本機校正・オフセット印刷・デジタル印刷・特殊加工・デジタルバーコ・デジタルグラマラス箔などを手掛ける総合印刷会社、株式会社セントラルプロフィックス。同社の営業部隊を支える営業管理部 営業支援課で期待を寄せられているのがリーダーの福澤悠貴氏である。入社7年目を迎え、仕事への責任感も一層強くなっているという。仕事内容について話を伺った。

印刷に関する知識を積極的に習得
今回、取材を受けていただいた福澤悠貴氏は長野県出身。神奈川県内の大学を卒業し、2019年4月に新卒で㈱セントラルプロフィックスに入社した。「大学では工学部でモノづくりを学びました。就職活動時に当社を紹介され会社説明会に参加し、印刷会社の仕事を初めて知りました。特にアニメが好きだったこともあり、そのパンフレットやポスター、ノベルティなどの制作を手掛けているのを目の当たりにして、そのような仕事をしてみたいと思い入社することに決めました」と、入社までの経緯を述懐する。

福澤氏は「営業の仕事に携わることによって、会社の仕組みや仕事の流れを知ることができると思い、営業志望でエントリーしましたが、面接で営業管理部 営業支援課を勧められお受けしました」という。
入社後は2ヵ月ほどの全体研修を経て営業支援課に配属され、先輩社員について実際の業務を教わった。営業支援の実務も少しずつ任されるようになったという。
営業支援課では、営業担当者が受注した案件を社内窓口として受け取り、営業担当者が本来の営業活動に集中できるよう、社内生産や外注手配の管理業務を中心に担当すると共に、営業部隊のシンクタンクとして各種リクエストのソリューションを担っている。
「まず営業担当が基幹システムに受注した案件内容を入力すると、仕様書が作られます。その仕様書に沿って営業支援課が、社内外のスケジュール調整、協力会社の手配、資材発注などを受け持ちます。案件によって社内一貫体制で仕上げられるもの、外部委託のものというように振り分けて、適切な管理を心掛けています」とのことだ。
同社の営業支援課は7名体制とのことで、1人当たり5名程度の営業担当者を支援。「基幹システム内のデータはチーム内の誰もが見られるようになっていて、お互いの仕事をフォローし合えるようになっています」とのことだ。
なお、これまで長年使っていた基幹システムを6月下旬に刷新したとのことで、気持ちも新たに仕事に臨んでいるようだ。「営業から加工方法の相談を受けた際に、現場の担当者と打ち合わせを実施し、金額を算出して営業へ伝えるのも業務として大きなウエイトを占めます。設計が肝であるため、加工の仕様から印刷版面設計をして営業に伝えています。見積書の作成に対しても、お客様に最適なものが提示できるよう知識を身につけるようにしています」と、見積書作成の支援も行っている。


後輩が初めて配属されモチベーションが向上
「印刷物というのは、デザインがそれぞれ異なるため、同じ印刷内容の仕事はほぼないのが実情です。そのため、何が最適な印刷や加工であるのか、知識がないと提案することができません。そうした知識を得るために協力会社を訪問し、実際の機械を確認しながら加工方法などへの理解を深め、最適な知識を得るようにしています。それによって、実際の発注に活かしたりして、より良い提案ができるようにしています」と、知識習得の積み重ねが重要だと語る
同社ではデジタルスポットUVコーター「Duplo DDC-8000」を導入していることから、厚盛箔加飾などの特殊表面加工なども得意としている。「拘りを持っているお客様からの引き合いが多いのが特徴です。チラシやパンフレットの受注だけでなく、ブランドブックや高級な紙袋といった高品質な印刷物のお仕事をいただくことも多いです」と、昨今の受注状況を話す。
営業支援課におけるスキルアップについては、「ありとあらゆる印刷・加工に関する情報や細かに仕組みを勉強した上で、最適な手法を提示できるようになることが求められると思います。例えば、製本の加工方法においては、この製本の仕方ではこの面付方法は不適合であるとか、このサイズでは加工できないということを、営業から相談を受けた時に最適な方法を提案できることです。そして、そのような知識を部署内で共有し、レベルアップを図っていければと考えています」と、的確な製作方法を指摘できる力の重要性を強調する。
実は、福澤氏が入社して営業支援課に配属された時は、一番年下だったという。「皆さん40代以上の方たちばかりでしたので、リーダーに抜擢された時は戸惑いましたが、皆さんから祝福されて、『ぜひ頑張ってほしい』と声を掛けてくれました。本当に嬉しかったです」と、リーダーに就いた時のことを振り返る。
今春、この課に初めて新入社員が配属され、ようやく一番年下ではなくなった。「後輩ができたことで責任感が一層増しましたし、モチベーションも一層高まった感があります」と、次代を担うリーダーとしての意欲を見せる。
「古い価値観に囚われず、高付加価
のモノづくりに励んで、常に新しいことにチャレンジできる会社にしていきたいです。その一翼を担っていければと考えています」と、締めくくった。

|